名瀬市街の国道沿いの大島高校前のバス停近く。

目立つ黄色の建物です。

ビデオシアター名瀬。

アダルトDVDも販売されています。

名瀬市街の国道沿いの大島高校前のバス停近く。

目立つ黄色の建物です。

ビデオシアター名瀬。

アダルトDVDも販売されています。

名瀬のブロック塀には、この塀が境界面であることを表す表記が彫られているものを多く見かけます。

こちらの塀には、塀が作られた年月が記されています。

幸町の住宅地で見かけたブロック塀。

←が書かれていて、塀のどちらの側が外面であるかが示されています。

奄美市名瀬幸町にある理容室。すばらしい木造の建物です。

水色を基調とした爽やかな明るい店構えです。

道路を挟んだ反対側には白を基調とした木造の理容室があります。

明治時代の擬洋風建築のような趣のあるモダンなデザインです。

屋仁川通りの交差点の角に、看板建築の建物があります。

1階には、スナックが3軒。

左側のスナックは、通路を進んだ奥に入口があります。

夜になると明かりが灯ります。
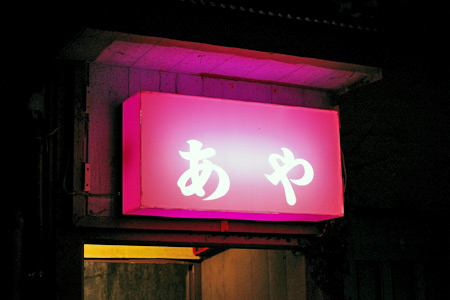
昭和33年の売春防止法の施行により、赤線廃止後は屋仁川の料亭料理屋は衰退し、バーが雨後の竹の子のように出現しました。*1

現在の屋仁川通りは、バーやスナックが建ち並ぶ歓楽街になっています。

昔の雰囲気を残すスナックの建物。

看板は取り外されていますが、スナックの建物だったのだと思います。

【参考文献】
*1 草戸寥太郎:ヤンゴ物語(屋仁川通り物語)-三味線(サンシン)と酒(セー)と女(ウナグ)の情景(奄美協同印刷,1997)P.17
名瀬の「ヤンゴ」は、旅人の憩いの場所として長い間愛されてきた名所です。「ヤンゴ」というのは、「屋仁川」の方言読みで、もとは川の名前でした。名瀬の料理屋は、はじめは町の中心部にありましたが、料理屋が町の中にあるのは風紀上よくないという理由で、明治44年、屋仁川通りへの移転通達が出されました。*1

現在、屋仁川(ヤンゴ)通りには、ピンク色のゲートができていて、「やんご生誕100年記念」*3 と書かれています。
戦前まで名瀬では、料理屋のことを「ヅリヤ」と呼んでいました。「ヤンゴ」は屋仁川全体の名称で、「ヅリヤ」は料理屋そのもを指す言葉でした。男たちは、「ヤンゴに行こう」という言い方をし、女房たちは「ヅリヤウナグのところか」などという言い方をしました。屋仁川の女(ウナグ)のことを「ヅリヤウナグ」と言ったのは、沖縄、奄美に徳川時代からいた「ヅレ(遊女)=沖縄では尾類(じゅり)とも言う」をあとで出現した屋仁川の酌婦に対して呼び名にしたものです。*1
「ヅレ」の本来の能は、歌舞をもって各地を巡り、アソビ(歌三味線の酒宴)の庭に列なることでしたが、大正時代中期に「ヅレ」は姿を消し、彼女たちに代わって、名瀬、古仁屋のヤンゴー地域に巣食う酌婦が出現しました。*2

昭和二十二、三年頃のヤンゴの料理屋は、屋仁川通りの道筋の東側の方に多く散在していました。*1

今の園田商店のところの四辻を右折したあたりが料理屋街の中心地でした。*1

【参考文献】
*1 草戸寥太郎:ヤンゴ物語(屋仁川通り物語)-三味線(サンシン)と酒(セー)と女(ウナグ)の情景(奄美協同印刷,1997)P.7,P.16-P.25,P.56
*2 金久正 著:奄美に生きる日本古代文化.復刻(南方新社,2011)P.134
【参考URL】
*3 観光ネットワーク奄美:奄美便り「やんご生誕100年祭 大やんご祭り」
今回は、名瀬(鹿児島県奄美市)の町並みと風俗を散歩します。
名瀬の背後に位置する「おがみ山」には、展望公園があります。

坂道を登っていくと、徐々に展望が開けていきます。(写真中央に、ティダモール中央通りのアーケードが見えます。)

展望台からは、山と海のはざまに密集する市街地が名瀬湾を囲むように広がっている様子が見て取れます。

公園の高台には、復帰記念碑が建てられています。
終戦後、奄美大島は本土から分離され、8年の長きにわたって米国の政権下に置かれ、1953年(昭和28年)12月25日に本土に復帰しました。

琴平には、美容室や理容室が数軒あります。

交差点の角にある理容室。

木造の佇まいが美しい美容室。

「銀座美容」と書かれた看板。

昭和33年(1958年)に琴平新地遊廓の歴史は閉じましたが、その後もその跡地はソープランドやバー・スナックが散在する「夜の街」という性格を現在も持ち続けています。赤線当時は参詣客が主でしたが、現在は地元の常連客が主になっています。*1

表参道脇にあるラウンジ。

稲荷神社の隣のスナック。

参詣客を相手にした門前町特有の賑やかな色街から、赤線廃止後徐々に、地元の人に利用されるこじんまりとした盛り場へと変遷していきました。*1

【参考文献】
*1 前島裕美:お茶の水地理 42 P.77-P.80 「香川県仲多度郡琴平町新地遊廓周辺の復原」
新地への入口があった路地*1 は、当時の雰囲気が保たれています。

赤線跡の建物。*2

白と黒のコントラストが美しい建物です。

向かい側の和風の建物。

【参考記事】
*1 風俗散歩(琴平):新地への入口
【参考文献】
*2 木村聡:赤線跡を歩く(自由国民社,2002)P.89
琴平新地は、一般の民家や旅館に隣接していて、塀や柵に囲まれることはありませんでした。

しかし、参詣者用に2か所の入口が設けられていて、そのうちの1か所にはアーチが建てられ、「新地入口」と書かれた傘のついた電気がぶらさがっていました。そのアーチの支柱は今も残ります。*1

旅館脇に支柱の一部と思われる痕跡が残されています。

もう一つの新地への入口は、現在の新町商店街の中ほどにありました。*1

【参考文献】
*1 前島裕美:お茶の水地理 42 P.77-P.80 「香川県仲多度郡琴平町新地遊廓周辺の復原」
表参道をそれて裏小路に入ると、ソープランドやスナックが散在する一角が出現します。

このあたりは栄町と呼ばれ、今でこそ人通りは少ないが、数十年前までは琴平屈指の盛り場として賑わいを誇り、現在の表参道沿いをすら凌駕していました。賑わいの理由は、参詣者の目当ての一つである遊廓があったためです。*1

昭和33年の売春防止法施行以降、遊廓の歴史は閉じましたが、その後も跡地は、ソープランドやバー、スナックが散在する「夜の街」という性格を現在も持ち続けています。*1

栄町の西側を流れる金倉川から見ると、川沿いにソープランドの建物が連なる景観に驚かされます。

【参考文献】
*1 前島裕美:お茶の水地理 42 P.77-P.80 「香川県仲多度郡琴平町新地遊廓周辺の復原」
今回は、琴平(香川県仲多度郡)の町並みと風俗を散歩します。
琴平には、山腹の社殿までの石段の数の多さで有名な金刀比羅宮、通称「こんぴらさん」があります。

表参道には参詣者が常に往来し、それに面して大型旅館・ホテル、参詣者向けの土産物屋が並びます。

古い門前町としての琴平の遊廓は、金山寺町(現在の通町、小松町)にあって、茶屋、賭場、富くじ小屋、芝居小屋などが建ち並ぶ遊興の地でした。しかし、一般の商店や旅館との混在は風俗上有害であるという理由から遊廓は明治33年(1900年)に、現在の栄町に移転され、新地と呼ばれることになりました。*1

金山寺町は、色街という性格は失いましたが、「琴検」と通称された芸妓検番が置かれ、娯楽の地として賑わいを続けましたが、時代の推移とともに衰退し、昭和56年(1958年)に検番も廃止されました。*1
地元の方の話によると、最後に検番があったのは、現在の饅頭屋の「灸まん」がある場所でした。

【参考文献】
*1 前島裕美:お茶の水地理 42 P.77-P.80 「香川県仲多度郡琴平町新地遊廓周辺の復原」
下津井の西町。

牛乳箱のある古い民家。

黒田牛乳の牛乳箱です。箱の中央に「K乳」のマークが配置されています。

木造の建物には、木製牛乳箱がよく似合います。

下津井は海岸線に沿って、軸となる道が通り、その両側に町並みが形成される近世港町の典型的な都市構造となっていますが、実はそれ以前の中世に背後の丘陵に向かって井戸と祠のある生活空間がひろがっていました。*1
下津井の町並みにはいくつもの井戸が点在し、「下津井共同井戸群」として文化財登録されています。

生活空間をなりたちを嗅ぎ取ることができます。

同じ場所の奥まったところにある別の井戸。

同じような井戸が何カ所かあります。

【参考文献】
*1 陣内秀信,岡本哲志:水辺から都市を読む(法政大学出版局,2002)P.347
下津井港に北前船がくるようになったのは、18世紀後半からで、秋になると何十艘という船団を組んできたので、これを迎える港町はてんてこ舞いの忙しさでした。北国の船頭をもてなすために地元の遊女のほかに他の港から応援を求めたり、港の素人娘をかり集めたりしました。*1

下津井の花街は、祇園神社の裾野の西町付近にひろがっていました。*2

「下津井懐古」*1 に掲載されている元遊廓と思われる木造三階の建物。

西町の奥の道がカーブするあたりに建っています。

【参考文献】
*1 中西一隆,角田直一:下津井懐古(手帖舎,1989)P.42,P.64-P.65
*2 陣内秀信,岡本哲志:水辺から都市を読む(法政大学出版局,2002)P.345 「下津井の都市構成図」
下津井で見晴しのよい所といえば、祇園神社です。

石段を登ると、瀬戸内海と瀬戸大橋を一望できる大パノラマが眼前に広がります。

祇園神社の玉垣には、加賀、能登、越中、越後の商人、船頭に交じって、寄付をした遊女の名も刻まれています。*1

本殿の玉垣に芸妓の名前が刻まれています。入舟内小繁、三長内小三、川高内小美可、島津内玉一などの名が見えます。*2

【参考文献】
*1 加藤貞仁:北前船 寄港地と交易の物語(無明舎出版,2002)P.37
*2 角田直一:北前船と下津井港(手帖舎,1992)P.167-P.168
今回は、下津井(岡山県倉敷市)の町並みと風俗を散歩します。
下津井は、瀬戸内の代表的な近世の港町です。古い町並みの入口にあたる場所に「まだかな橋」の碑が建てられています。

まだかな橋跡。親柱が残されています。

江戸時代、入港してきた北前船などの船頭に、「まだ(遊廓に)あがらんかな」と声かけた婆がいたことから、この名が付けられました。

最近、建てられたと思われる「まだかな橋跡の碑」が道路の反対側にあります。

日比のハス停から日比港へ向かう途中の道。

日比市民センター前に白ポストがあります。

入口から入ると白ポストが目に入るように配置されています。

道路からは白ッポストの側面が見えます。

緩やかなカーブを描いて、古い町並みが続いています。。

昭和10年の日比町住宅明細図にも記載されている銭湯の八千代湯の建物が現在も残っています。

モダンな造りの銭湯です。

女湯の掲示が見られることから、この建物が銭湯であったことが解ります。

山側の通りの中ほどに、元旅館の建物が残っています。

繊細な格子を持つ建物です。

現在も旅館の屋号の表示が残されています。

建物脇の路地。

日比には、所々に古い町並みが残っています。

元妓楼の栄楼と思われる建物。*1

二階部分に手摺のあります。

遊廓の面影を残す和風建築です。

【参考文献】
*1 山田平次郎:日比町住宅明細圖(備讃民報社,1935)
今回は、日比(岡山県玉野市)の町並みと風俗を散歩します。

日比は、北前船の寄港地で、かつては商家や遊廓が並び、船が入ると賑やかな港町情緒を漂わせていました。*1
日比港の背後には、眼下に日比港が見渡せる日和(ひより)山があって、日比の遊廓から芸者を連れ出した船乗りたちは、ここで「日和申し」と称して飲食を楽しみました。*2

現在の日比港。江戸時代は、日比と対岸(写真奥)の向日比の二つの集落に分かれていました。

日比町住宅明細圖*3 によると、遊廓は海岸線に沿って並んでいたようです。

【参考文献】
*1 山陽新聞社:岡山県民の明治大正(山陽新聞社出版局,1987)P.259
*2 加藤貞仁:北前船(無明舎出版,2002)P.36
*3 山田平次郎:日比町住宅明細圖(備讃民報社,1935)
「千日前商店街」は、南北に連なる長大な岡山表町商店街の一部で、その南端に位置します。

「千日前商店街」のアーケードが尽きるあたりに、「岡山日活」があります。

成人映画のポスターが貼られた解りやすい店構えです。

シニアは900円と良心的な価格設定です。

今回は岡山(岡山県岡山市)の町並みと風俗を散歩します。
岡山市の市街地にあって最大かつ伝統的な街「表町」は、さまざま表情をもった商店街です。北側から南へ、上之町、中之町、下之町、栄町、紙屋町、西大寺町、千日前、新西大寺町と有り「表八ヶ町」と通称され、現在でもこの名で呼ばれることがあります。*1
この「表八ヶ町」の東の裏通りにあたるのが、旧町名で「内山下元町5丁目」(現在の表町2丁目4,5、内山下1丁目12,13)で、バーや喫茶店の多い町です。*2*3

現在も表町2丁目4,5付近は、スナックやバーが建ち並んでいます。

ポリバケツや洗濯機が置かれた路地の奥に「スタンド」の看板。上には洗濯物。エアコンの室外機の上には一升瓶が置かれています。

スナックのある路地。

【参考文献】
*1 協同組合連合会 岡山市・表町商店街連盟:おもてちょう「表町商店街の歴史」
*2 内山下地区連合町内会:2004年度版「内山下地区連合町内会」の地図
*3 岡山新聞社編集局:現代岡山町誌(岡山新聞社,1958)P.9-P.10