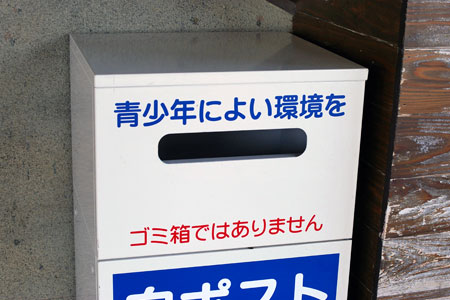桶屋町は、道路を隔てて東西に延びています。東の桶屋町は、昭和初期の建物が並ぶ住宅街となっています。格子の窓や、二階には木の手すりも多く残っています。*1

三代続く医者のお宅。*1

西の桶屋町は、遊廓があった柴屋町に接しているため、飲食店が軒を連ねています。建物には、昔、芸者置屋さんだった雰囲気が残っています。*1

桶屋町は、揚屋町として栄えました。遊客は、この揚屋へあがり、置屋から遊女を呼び出し、遊興を楽しみました。*1

【参考文献】
*1 大津の町家を考える会:大津百町物語(サンライズ出版,1999)P.62