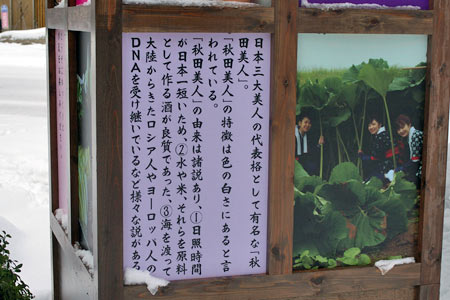今回は、歌舞伎町(東京都新宿区)の町並みと風俗を散歩します。
歌舞伎町公園前の通り。飲食店などが入る雑居ビルが建ち並んでいます。

「美少女戦士コスプレエンジェル」。風俗店と思われる看板ですが、それらしき店舗はすでにありません。店舗が閉店した後に看板だけが取り残されたようです。
「リボンの騎士」、「セーラームーン」などの「戦闘美少女」は、わが国固有の表現ジャンルで、アニメ系コスプレ風俗が一部で流行りました。*1

1Fにパチンコ店が入るビル。ビルの角の上部に「ローラン」と書かれています。

ノーパンしゃぶしゃぶの店として有名だった「ローラン」。現在は看板だけが残っています。

【参考文献】
*1 斎藤環:戦闘美少女の精神分析(筑摩書房,2006)P.8,P.80