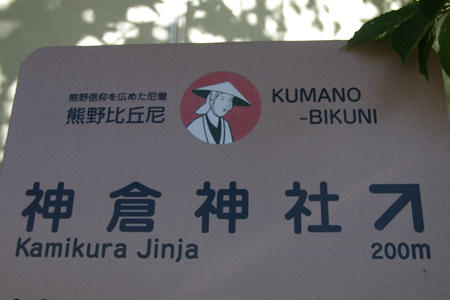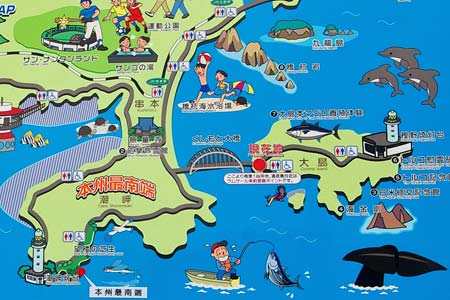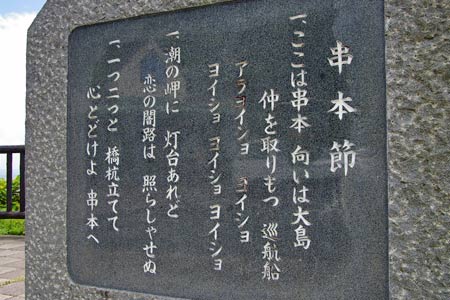今回は古市(三重県伊勢市)の町並みと風俗を散歩します。古市遊廓跡の入口にあたるのが「間の山」の坂道です。遊廓が全盛だった大正時代の間の山は、今よりも坂が急でしたが、人力車は威勢よく行き来しました。*1

間の山の坂の途中に、「お杉・お玉の碑」があります。
お杉・お玉というのは、二人の女性が三味線を引きながら演技をしているのに対して、お客がほんのすぐ近くから小銭を投げるのですが、それを女たちがたくみにバチで受け止め、これを避けたりして体にあたらないようにする遊び場で、古市の見世物のひとつでした。*1

間の山は、井原西鶴の「西鶴織留」や中山介山の「大菩薩峠」にも登場します。*1

間の山の近くの「まちづくり実行委員会」の民家に、当時の古市の写真が掲載されています。

【参考文献】
*1 中村菊男:伊勢志摩歴史紀行(秋田書店,1975)P.108 -P.110