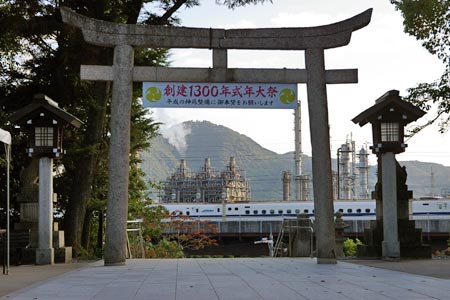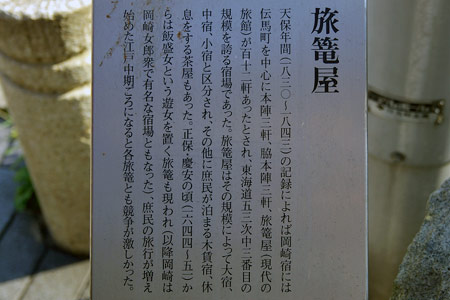戦前まで、現在の栄町にあった才ノ森遊廓*1 は、昭和20年7月の空襲で焼失し、その後、昭和25年に下御弓(しもおゆみ)町に移転し、その一画を柳町と命名し、昭和33年4月1日に赤線が廃止されるまで続きました。*2
「昭和10年徳山市街図」*3 を見ると、「下御弓丁」と書かれた場所は、現在の昭和通り沿いの川端町、柳町、橋本町、飯島町のあたりであることが解ります。中でも、現在も柳町の名が残る界隈は、昔の風情が残るスナックなどの飲食店舗が密集しています。

和風の古い建物をスナックに改築した建物が随所に残っています。

洋風の建物。

2軒の店舗を有する大型の民家。

【参考記事】
*1 風俗散歩(徳山):才ノ森遊廓跡地(2009.10)
【参考文献】
*2 前田麦二:徳山の思い出(マツノ書店,1985)P.42
*3 同上 P.153 「徳山商工会編 昭和10年徳山市街図」