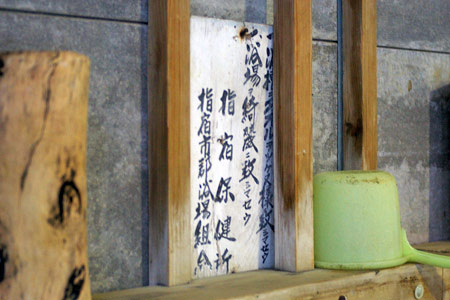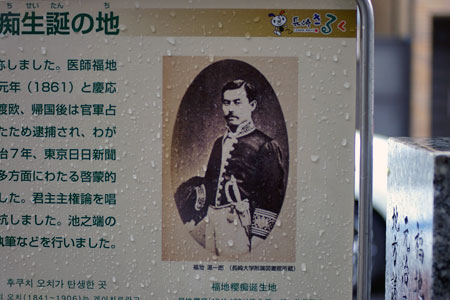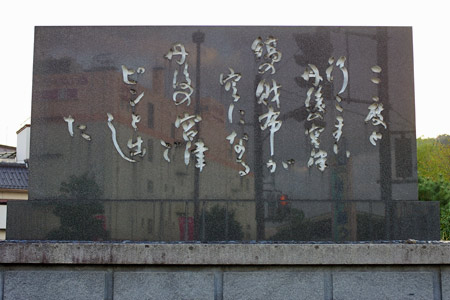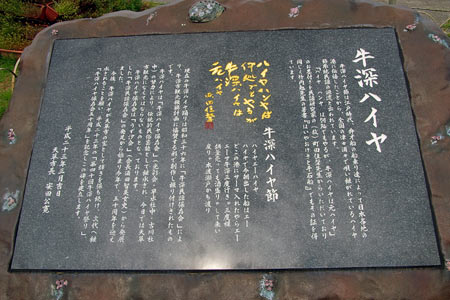道頓堀川の大黒橋近く。屋上にトルコ風呂の看板が残るビルがあります。

「トルコ孔雀」と書かれています。
1981年の資料*1 によると、ミナミ(難波駅周辺)には、約30軒のトルコ風呂が営業しており、この写真の付近には、「孔雀」、「六本木」、「男爵」の3軒の店が建ち並んでいました。

ビルの背面(道頓堀川側)。

”和風”トルコだったようです。

大坂のトルコ風呂は、条例によって、個室の天井に近い壁に20~30センチの空間(隣の部屋とのスキ間)を作るよう定められていたのが特色でした。これにより、隣の部屋の話声、シャワーの音などがソックリ聞こえるので、少々プレイのさまたげになったのですが、店側が一部屋ずつ置いて客を入れることで解決しました。*1
【参考文献】
*1 大洋図書:ミリオンMOOK全国高級トルコ・ガイド(大洋図書,1981)P.106-P.110