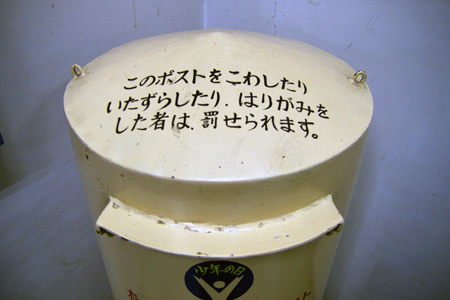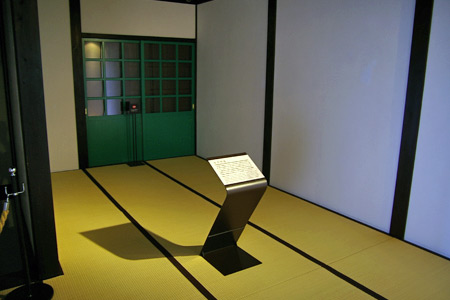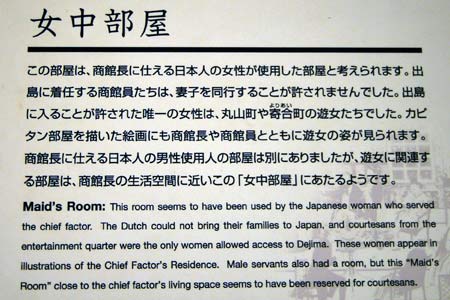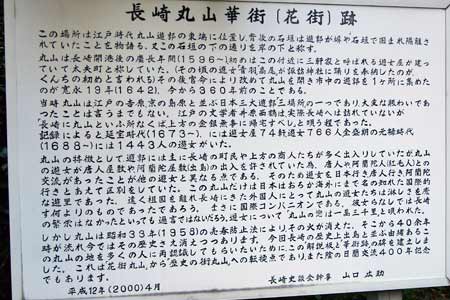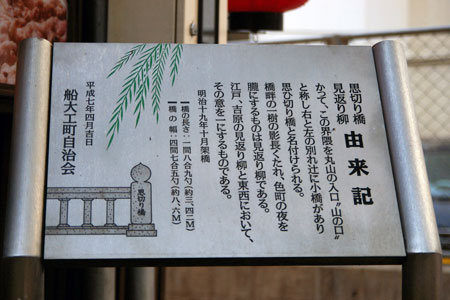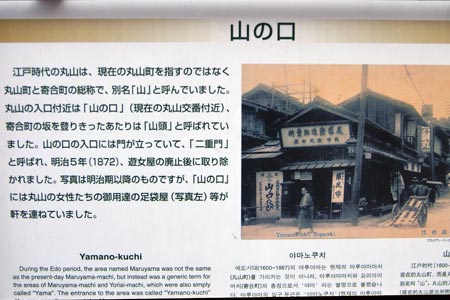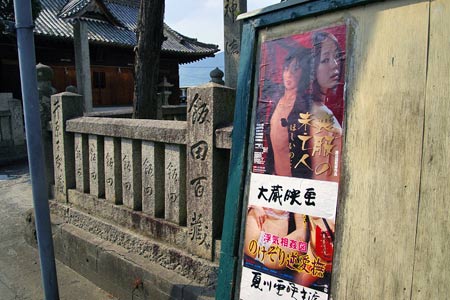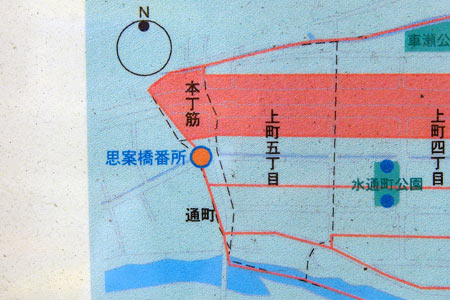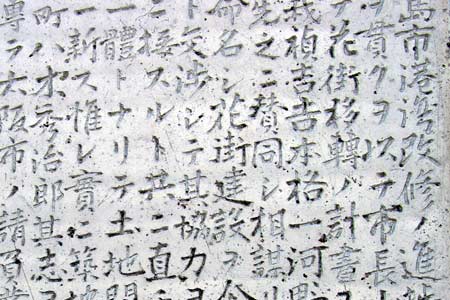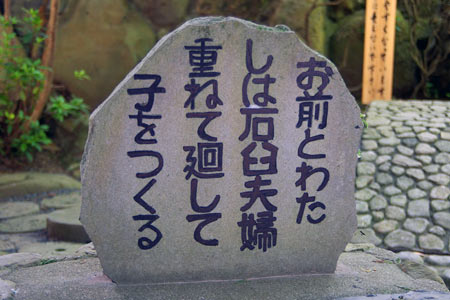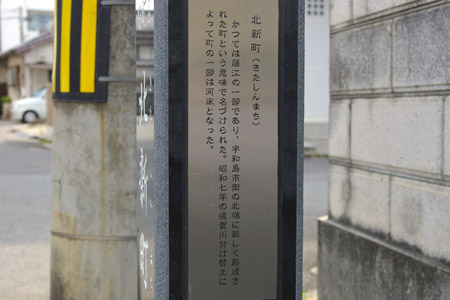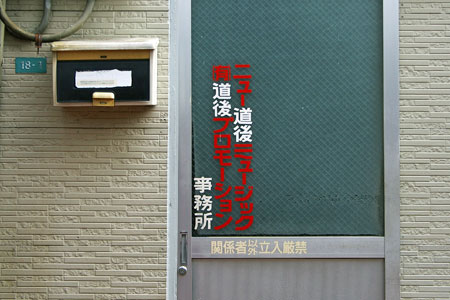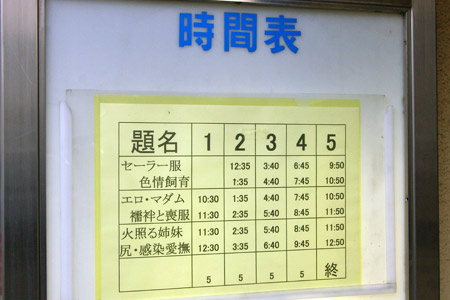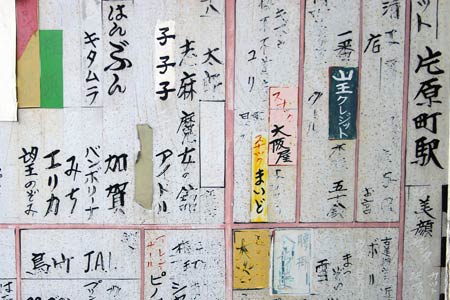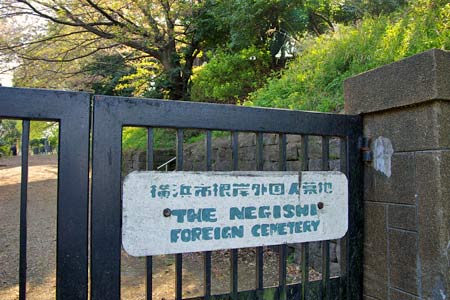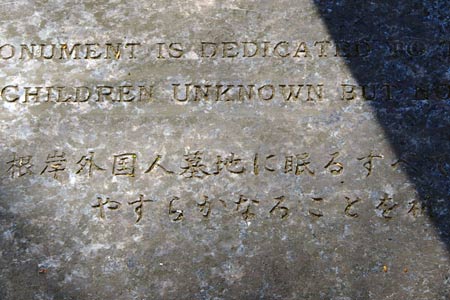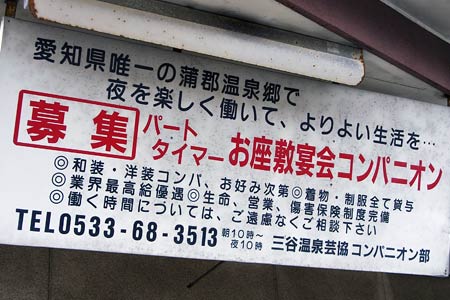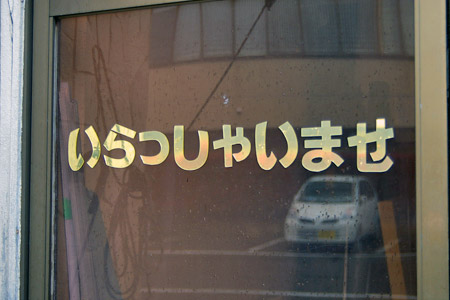二本木遊廓にあった東雲楼は、廓中第一流の大籬(おおまがき)としてその名を全国に知られた遊廓でした。構内は広く、数棟の巨屋が軒をならべて建ち、広大な庭園を有していました。*1
東雲楼の一部の建物が現在も残っています。*2
残念ながら近日中に取り壊されることが決定されているようです。

1900年(明治33年)、東雲楼の娼妓たちが待遇改善を求めてストライキを決行。東雲楼は、一躍有名になりました。*3

玄関の床のタイル。

当時のままと残されているレンガの塀*2

【参考文献】
*1 津留豊:熊本の遊びどころ(舒文堂河島書店,2006)P.37(明治42年発行の同名の書籍の復刻版)
*2 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002)P.59
*3 佐渡資生:味と歓楽五〇年 くまもと夜話(味と歓楽50年出版委員会,1984)p.171